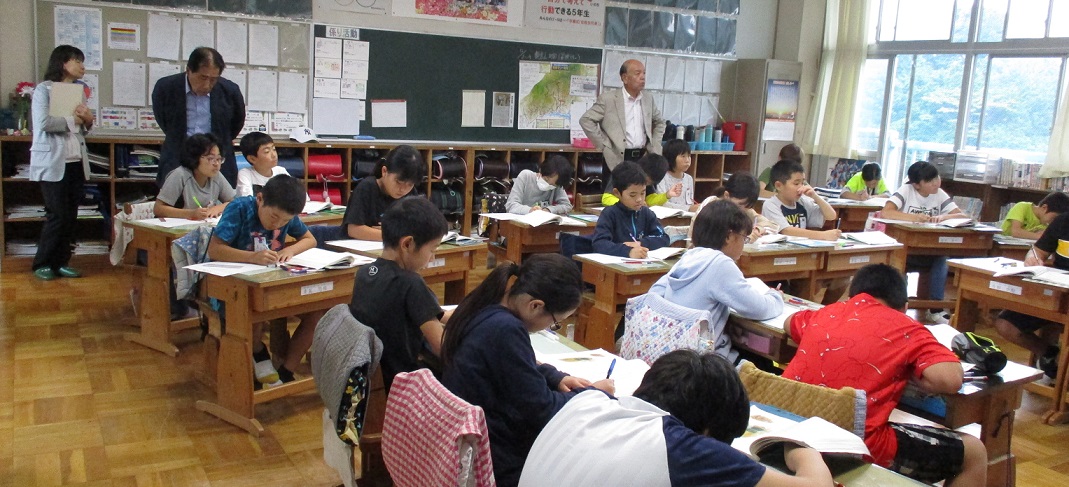子どもたちへのお話
新年の挨拶をしたいと思います。「明けましておめでとうございます」。ここにいる全ての人にとって、良い一年になることを心から願っています。
2学期の終業式の折にみんなに宿題を出しました。「他の人にはない自分の強みを探してみる」ということでした。見つけることはできましたか?そして、穏やかな良いお正月を過ごすことができましたか?
私は、正月三が日の中で、学校に来ることがあったのですが、その時に偶然、校門の前で写真を撮っているご家族にお会いしました。聴くと、この4月に本校に入学してくる女の子がお父さん・お母さんと一緒に通学路を歩いてきたというのです。そのご家族の微笑ましい光景から、これから始まる学校生活にどれだけ希望と期待を抱いているかを知ることができましたし、私たち学校で働く者たちは、こういった思いに十分に応えられるように一層頑張らなければならないと強く感じました。
終業式の時には、「学校がさらに良くなるために、まずこの学校の強み(他の学校にはない向笠小だけの良さ)は何かというところから考えてみた」ということをお話ししました。今日は、そのことを中心にお話をしようと思います。
学校の強みの一つ目として、みんなのことを挙げたいと思います。それは、自分たちで「やろう」と決めたことは、一生懸命取り組むことです。力を抜いたり、ズルをしたりせず、ひたむきにやるべきことに向き合うことができます。持久走記録会や学習発表会、運動会等を見ていてそう感じました。このひたむきさは、他の学校にはないみんなの良さです。だから、先生たちもみんなの良さをもっと引き出すために、先生たちが何でも指示するのではなく、みんなの「やりたい」という気持ちを引き出し、その「やりたい」を実現させるための方法もみんな自身で考えるような機会をどんどん増やしていきたいと考えています。
二つ目は、この学校は市内でも子どもの数が少ない、小さな学校であるということです。大きな学校には大きな学校の良さがあるように、向笠小学校のような小さな学校には小さな学校の良さがあると思うのです。その良さの一つとして、いろいろな学年の子と仲良くなる機会がほかの学校に比べて多いということです。例えば、低学年の子は高学年の子といっぱい活動する中で、大きくなったらこんなことができるようになろうって思えるでしょう。逆に高学年の子は、低学年に格好悪いところを見せられないっていつもより頑張るかもしれないし、低学年の子が困っていたら自然と手を差し伸べる優しさが身につくということもあるでしょう。だから、これからは今まで以上にいろいろな学年の子と活動する機会を増やしていきたいと考えています。学年掲示板を見ていると、5年生の山崎瑛子さんがすばらしい提案をしたノートのコピーが貼ってありました。それは、これからの社会をつくっていく私たちは、仲間と協力して未来を作っていかなければならない、そのためにも「他の学年の子との関わりを増やす」ことが必要だというのです。具体的には、学級遊びを他の学年と合同で行うということ、さらに仲の良い人を5人以上作るというものです。どうですか?こういったことなら、今からでもできそうではありませんか?
三つ目は、この学校は地域とのつながりがとても強いということです。どの学年でも地域の作物を育てて、それを食べるという活動を行っています。この活動を行うには、地域の方々のサポートも受けています。このようなことができている学校は他にないと思います。さらに、毎日の登下校では、地域の方々が通学路に立って、みんなの安全を見守っています。だから、今後とも地域とのつながりを大切にした活動を行っていきたいと考えています。これについては、みんなにも考えてほしいことがあるのです。本校は、他の学校以上に多くの地域の方々のお世話になっていると思うのです。こうやって、お世話されるばかりでいいのでしょうか?自分たちで地域のためにできることはないでしょうか?これを難しい言葉で「地域への貢献」というのですが、貢献できそうなことを一つでも二つでも考えて取り組めるといいなと思っています。
こうやって考えていくと、向笠小は無限の可能性を秘めたすばらしい学校だと思います。皆さんも「こんなことをやりたい」「こんな学校にしたい」というアイディアを思いついたら校長室に教えに来てください。一緒にいい学校にしていきましょう。これで、始業式のお話を終わります。
子どもたちへのお話
本日は、寒さを緩和することやインフルエンザ等の感染拡大を防ぐことを鑑み、放送による終業式を行いました。各学年の代表児童のことばや、校長からの話について、子どもたちは各教室で放送を聴くようにしました。ここでは、校長の話を紹介します。
2学期を振り返ってみると、みんな、本当によく頑張ったと思います。1・2年生はお店屋さんを作って幼稚園の子どもたちを招待し一緒に遊びました。さらに1年生は自分たちで育てたさつま芋を使って料理しましたし、2年生はグループで町探検を行いました。3・4年生は社会科見学を行い積極的に見たり聞いたりしました。さらに3年生はそばの実を育ててそば打ちまで行ったし、4年生は様々な福祉体験を行いました。5・6年生は観音山自然体験教室・修学旅行とみんなで泊まっていろいろな体験をするという行事がありました。さらに、校外行事として、4年生と5年生の一部は音楽発表会へ、6年生は水泳大会・陸上大会に参加し、自分の力を精一杯発揮しました。
もう一つ紹介しておくと、2学期は82日間、学校に来る日があったのですが、1日も休まずに登校できた子は75人いました。これも頑張ったことの一つですね。ちなみに1学期からまだ1日も休んでいない子は46人います。すごいですね。
私は、みんなの純粋な笑顔に心温まり、ひたむきに頑張る姿に心が熱くなりました。素直にありがとうと言いたいと思います。それだけでなく、そんな皆さんにとって、この学校がさらに良くなるためにどうすべきかを私はずっと考えてきました。そのため、この学校の強み(他の学校にはない向笠小だけの良さ)は何かというところから考えてみました。この具体は3学期にお話ししたいと思いますが、強みを見つけるたびに、私の心に変化が生まれました。
それは、向笠小のことがますます好きになっていったということです。「向笠小はいいところがいっぱいあるなあ。やっぱり向笠小はすごいなあ。」と思えるほど、好きになっていったのです。それだけではありません。
ここにいるみんなとなら、そしてここにいる先生たちとなら日本一の学校にだってなれるって自信もうまれてきたのです。
そこで、私からみんなに冬休みの宿題を一つ出します。私がこの学校について考えたように、みんなは自分自身のことについて考えてみてください。「他の人にはない自分の強みって何だろう」って。それが見つかるたびにきっと自分で自分のことが今まで以上に好きになり、「ぼくは(私は)きっとやれる」と自信も生まれるはずです。
では、12日間のいい冬休みを過ごしてください。そして、1月7日には全員そろって笑顔を見せてください。
教師向けの話
職員会議の冒頭で、校長から全職員に話をしたことの概要をお伝えします。
1 2学期の総括を
3学期はあっという間に過ぎていきます。3月までにどのような子どもの姿を目指すのかを見据えたうえで、現在の成果と課題を明確にしておきましょう。3学期以降は、学年だよりにも学級経営に寄せる学級担任の思いをもっと書くように工夫してみましょう。
2 場を整えることの大切さ(子どもたちがじっくり考え、主体的に活動するために)
(1)来校者が必ず口にする言葉
来校者があると、必ずと言っていいほど、「こういった環境で学べる子どもは幸せですね」と口にされます。これは、自然に恵まれていることの良さを指しているのでしょうが、では、なぜ自然に恵まれていると幸せなのでしょうか。これは、落ち着いた雰囲気の中での教育活動ができるということを指しているのでしょう。このことは、明らかに本校の強みの一つと言えます。したがって、校舎内についても落ち着いた雰囲気を整えることが必要だと考えます。
(2)目指す子どもの姿
子どもたちには、ごみや埃に自分で気づき、自らきれいにするといった姿を望みます。自分の足元にゴミが落ちていても気づきもしないのはやはり寂しいです。さらに、机や自分の荷物を整理しようとする姿も望みます。「自分の荷物だからどのように置こうが自分の勝手」ではいけない。他の人が見たときに、やはりいい気持ちはしませんから。
(3)教師も環境の一つ
教師自身も環境の一つであるとよく言われます。心掛けてほしいこととして、学級掲示をすっきりと、歩みや担任の思いが分かるものにしてほしいということです。さらには、居ずまい(服装・言動)を整えるとともに、子どもの育ちを待ち、余分な教師の指示などは控えるようにしたいものです。
3最近の教育に関する記事から
最近の新聞記事の一部を紹介します。これらのことからも、日本の教育は子ども主体の探究学習を重視する方向に向かっていると言えます。だからこそ、新学習指導要領においても、探究を進めるための計画を自ら立て、学習途上での軌道修正を行い、最後までやり遂げようとする、いわゆる「学びに向かう力」をつけるように求めています。保護者からの学校評価アンケートにおいても、授業のあり方について多くの意見をいただいています。今後、さらなる授業改善が必要だろうと考えています。
(1)市民団体による校則調査(浜松) 12.12
市民団体は、息苦しく軍隊のようなルールと評し、市教委担当者は「守れというだけでなく、きちんと理由も説明していきたい」と説明しています。教師は「やりなさい」と指示するだけでなく、誰にもわかるような丁寧な説明を行えることが必要だということです。
(2)PISA調査 「自分の考えを根拠を示して説明」課題
天声人語(朝日新聞)12.4に、PISA担当者の言葉として、「細かな知識はネットで得られる。知識よりも知恵を出して事態を突破する力が求められる。」という言葉がありました。まさに今後の授業改善を行う上での一つの指標になるでしょう。
(3)「教育」から「伴走」へ(12.5中日新聞夕刊 紙つぶて:今村久美)
次の言葉が非常に印象的でした。これからの学校教育においても、全く同じことが当てはまると思います。
○大人が子どもに正解を教え育てる「教育」から子どもの気づきを大人が支え育む「伴走」に切り替えるとき。
○「やってみたい」という意欲を育み、「やってみた」経験を学びに変える支援こそ大人の役割ではないだろうか。
○育みたいのは、問いを立て、学び続けられる自律した学習者だ。
(4)中教審初等中等教育分科会論点整理(10.16 静岡新聞朝刊)から
下の言葉が印象的でした。集団で学ぶことの意味や意義を再確認し、授業改善を進めていく必要があると強く感じました。
○論点の一つとして、「義務教育段階では児童生徒同士、児童生徒と教師が顔を合わせ学級でともに学ぶ意義を再確認する」の文言があった。
○分科会会長代理の弁として、「技術によって目指している公正で個別最適化された学びが実現すれば、今の学校の常識が通用しなくなる可能性がある。(中略)同じ学年の子どもが同質集団を形成している今の学校は成り立たなくなるかもしれない」との文言が紹介されていた。
保護者向けの話
磐田市では、今年度から、学校と市(行政)の「顔が見える関係」をつくり、人づくりという大括りの施策の中で、相互協力・支援を進めていこうという目的のもと、市役所の各部局長が分担して市内小・中学校を訪問してくれる「心合わせ」プロジェクトを行ってくれています。
この日(12月12日)は、本プロジェクトの一環で建設部長に訪問していただきました。この訪問に際して学校側からは、「向陽坂と馬坂は通学路になっているが、大規模の台風や地震による影響がこわい。今年度も倒木が何度かあった。PTAの方々も大変心配している。市として何らかの方策を取っていただけないか相談したい」と事前にお話をしてありました。
建設部長さんは、来校してすぐに、「学校側から相談を受けた件について確認したところ、向陽坂の一部で土砂災害特別警戒区域※に含まれる箇所がありました。そのため、早急に調査実施後、対策を講じていきます。さらに、倒木についても、地権者と相談していきます」との説明をしていただきました。
学校側の心配を前向きに受け止めていただき、子どもたちの安全・安心を市として担保したいという強い気持ちを感じることができました。私たちにとって、とても嬉しく、心温まる訪問になりました。
※ 静岡県地理情報システムから確認できます
教師向けの話
先日、ある方にこの詩を紹介していただきました。私は、この詩に出会ってから、何だか心が軽くなった感がしています。
この詩は、新婚夫婦に対するものですが、教室での教師と子どもの関係、職員室内の同僚同士の関係、家庭での親子関係に置き換えても、十分にしっくりくるのではないかと思い、職員全員に紹介しました。
祝婚歌 吉野弘
二人が睦まじくいるためには
愚かでいるほうがいい
立派すぎないほうがいい
立派すぎることは
長続きしないことだと気づいているほうがいい
完璧をめざさないほうがいい
完璧なんて不自然なことだと
うそぶいているほうがいい
二人のうちどちらかが
ふざけているほうがいい
ずっこけているほうがいい
互いに非難することがあっても
非難できる資格が自分にあったかどうか
あとで
疑わしくなるほうがいい
正しいことを言うときには
少しひかえめにするほうがいい
正しいことを言うときには
相手を傷つけやすいものだと
気づいているほうがいい
立派でありたいとか
正しくありたいとかいう
無理な緊張には
色目を使わず
ゆったり ゆたかに
光を浴びているほうがいい
健康で 風に吹かれながら
生きていることのなつかしさに
ふと 胸が熱くなる
そんな日があってもいい
そして
なぜ胸が熱くなるのか
黙っていても
二人にはわかるのであってほしい
教師向けの話
来年度の教育課程編成作業を行うにあたり、先日、校長として「どんな学校を目指していくのか」といった学校経営構想の概要を、全職員に説明を行いました。それが、以下の通りです。
細かな文言修正等は、今後多くの方々のご意見をお聞きしながら随時行っていこうと考えていますが、ホームページ上に公開することで、大まかな考え方について地域や保護者の方々にご理解をいただくとともに、ご意見などあれば直接、校長までご連絡いただければと思います。なお、今後はここに示された学校教育目標を具現化するための方策を全職員の知恵を絞って検討していく予定です。よろしくお願いします。
1 はじめに
(1) 校訓に込められた思い
校訓「誠実」は、本校教育の歴史を貫く最高理念として位置づけられ、本校創立当時の理念や意気を反映しており、建学以来、連綿と受け継がれてきた。
「誠実」には「まじめで嘘をいわない」「そのものに心を打ち込み、没頭してやり抜く姿」「気力が充実して、言行が一致している」といった向笠に集うものすべての基盤となる人間性を示している。今後も、この校訓に込められた先達の思い・地域の願いを受け継いで、学校経営を展開していく。
(2) 本校児童の強みを伸ばす
概して、子どもたちは「やってみたい」「挑戦したい」というまっすぐな思いをもって教育活動に取り組む。これは、紛れもなく本校の子どもたちの良さであり、今後さらに伸長すべく指導・支援に努めねばならない。
(3) 小規模を強みにした学校経営
本校の児童数は、今後も140名から150名程度を推移すると思われ、市内でも小規模校の部類に含まれる。この小規模であるという環境を、本校の持つ強みととらえ、学校経営を展開していきたい。
2 学校教育目標「瞳を輝かせ 最後までやり遂げる子(仮)」
校訓が学校創立当時から続く恒久的な理念だとすれば、学校教育目標は短期的な目標と言える。本校では、平成23年度から学校教育目標を「瞳 輝く子」とし、子どもの姿で、学校教育の目標を示している。「瞳 輝く子」に寄せられた思いとは、個が尊重される教育活動を基盤とし、主体的に学習し、生き生きと生活している姿を理想としてきた。
本年度は、これまで目指してきた子ども像をさらに進化させた形で、学校教育目標を「瞳を輝かせ 最後までやり遂げる子(仮)」と設定した。
(1) 瞳を輝かせ
ア 自主:自らを進んで伸ばそうとする。目の前の課題を自分の力で解決するために、分かりたい、できるようになりたいという気持ちを持つことや、「分からない」「○○をやりたい」ということを意思表示しようとする態度を育てる。
イ 自治:友達の個性や価値に気づき、ともにそれぞれの価値を磨きあい高めあおうとする。子どもたち自身がより良い学級、より良い学校を作っていこうとする態度を育てる。
ウ 貢献:ふるさとである向笠の地を愛し、自らを取り巻く社会や環境をより良くしていこうと自ら行動を起こす。
(2) 最後までやり遂げる子
どんなに難しいことがあっても逃げずに乗り越えることができ、自分の人生を楽しく充実したものとして創造することができる「たくましさ」を育てていきたいと考える。具体的には、「できるようになりたい」という思いを持ち続け、根気強く取り組む姿に加えて、周りの人(同学年のみならず様々な年齢の人々)とのつながりやかかわりを深め、一緒に課題を解決しようという態度も含んでいる。
以下に、この言葉を新たに学校教育目標として設定した理由について述べる。
ア 子どもたちの成長から
上述のとおり、「やってみたい」「挑戦したい」というまっすぐな思いをもって教育活動に取り組むところは、本校の子どもたちの良さであり、これまでの学校経営上の一つの成果であるとも言える。しかし、ともすると失敗を恐れ周囲に合わせようとしたり、教師に頼ってしまおうとしたりする姿も見られる。今後は、「やってみたい」と思ったことを、友達と協力しながら最後までやり遂げようという強い気持ちを育てていく段階に入ったと考える。
イ 本校の教育課題から
磐周小学校教育活動検討委員会答申(平成30年6月7日)において、「課題設定に主体的に関わったり試行錯誤を繰り返して追究したりする過程を忌避して、安直に結果を求めがちな児童も少なくない。(中略)昼休みは学校行事や委員会活動、放課後は課外活動、帰宅すれば塾や習いごとというパターンを解消して、じっくりと学習に取り組める環境を整えねばならない。」と述べられている。
このことは、本校の教育課程を見直す上においても重要な視点であり、行事や日課表等を見直す中で、子どもも教師もじっくり取り組める環境づくりを進める必要がある。じっくり取り組める環境を整えたうえで、子どもたち自身の「やりたい」を引き出し、そのことをやり遂げようというたくましい心を育てていかねばならない。
ウ 磐田市の目指す姿から
磐田市教育委員会は、磐田市の教育について、大きな変動が予想される未来に立ち向かっていける「たくましい磐田人(いわたびと)」を育成するために、家庭・地域・学校が連携し、地域総ぐるみで子育てに取り組んでいくと述べている。本校も、磐田市の教育の目指す方向性と歩みを同じにしていかねばならない。
3 学校経営目標 「夢を語ろう そして 一歩前へ(仮)」
(1) 向笠スピリッツ 「すべての子どもの笑顔のために」
向笠小の教職員として、「何のために仕事をしているのか」といった明確なビジョンを持っておきたい。私たちは、子どものために仕事をしているのである。あえて「すべての」という言葉を入れたのは、一人の子どもも一人ぼっちにしないという強い思いの表れである。
子どもたちは「やりたい」を見つけ、幾つもの課題を乗り越え、見事やり遂げたとき、きっと充実感と達成感で満ちた笑顔を見せてくれることだろう。そのような最高の笑顔のために向笠小の教職員は家庭や地域と連携しながら邁進する。
(2) 経営の基盤を支えるもの
向笠小の教職員が向笠の教育を推進する上で、いつも大切にしたい「経営の基盤を支えるもの」を以下の3点にまとめた。
ア 「いのち」を大切に
① 家庭との連携を密に図り、多面的・多角的な視点で子ども理解に努める。子ども理解に完成はなく、時間のかかる地道な作業となる。しかし、本校職員は「時間がないから子ども理解ができない」などと言い訳はしない。深い子ども理解のため、決して妥協は許さない集団であり続けたい。
② 他者とのかかわりやつながりを実感できる機会を多く設定することにより、自己への気づきを促し、自己を適正に評価できるように支援する※。そのため、教師による一斉指導は、笑顔で、冷静に、短時間で終わるよう心掛ける。授業において、意味のある対話(学び合いを意味づける、位置づける、成り立たせる)を意図的に単元の中に組み込んでいく。行事等を作り上げる過程において自然発生的に様々な異学年集団で活動できるよう支援する。小規模校であるが故、小回りが利いて様々な場面において様々な形態の小集団を作りやすいことを生かしたい。
③ 勤務環境改善を図り、教職員の「いのち」も大切にする。教職員が心身ともに健康であることで、子どもたちに笑顔で接することができ、このことが何より高い教育効果を生み出す。
イ 「チーム」として
① 小規模校の良さとして、教職員一人ひとりの個性と能力を発揮しやすいということも挙げられる。学校経営に貢献するために、教職員一人一人が自身の持ち味を生かし、「すべての子ども」のために全力を尽くせる教職員集団でありたい。
② 医療や関係機関との連携、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの積極的な活用により、一人ひとりの子どもにとって最適な支援のあり方を常に追求できるよう、チームとして取り組む。
ウ 地域とともに
① 向笠の地には、新豊院山墳墓群をはじめとする歴史を感じさせる様々な遺跡、桶ヶ谷沼や鶴ヶ池をはじめとする様々な自然、米やそばをはじめとする様々な農作物、何より本校には先達が整備したビオトープなど、他には類を見ない優れた教育素材が多く存在している。そこで、子どもたち自身がふるさとである向笠の地を愛する心が持てるよう、向笠の自然や地理的条件を生かした教育活動を意図的に創造していく。
② 現在も、本校では地域の方々の支援を受け、全学年で地域の作物を栽培し、加工して食べる「地産地消」の活動を推進している。こうした食農学習は向笠ならではの特色ある活動であるので、今後も積極的に推進していく必要がある。
③ 向笠小の学区は広く、中には土砂災害警戒区域に指定されている箇所もある。さらに交通安全上の課題を抱える箇所もある。しかし、そうした課題だけでなく、地域の見守りボランティアの方々が積極的に活動してくれているという強みもある。そこで、そうした地域の方々との連携を密に図り、防犯や事故ゼロに努めていく。
(3) 学校経営目標「夢を語ろう そして一歩前へ(仮)」に込めた思い
ア 夢を語ろう
子どもの「やりたい」を引き出すために、まず夢を語り合える職員集団でありたい。「できない」ことが先行する議論は閉塞感しか生まれない。授業改善への夢、異学年交流を充実する特別活動への夢、市内水泳大会や陸上大会が終了しても子どもたちの体力の維持向上にかける夢・・など、子どもの成長を肌で感じることができる教職員ほど、次から次へと夢は尽きないものである。
夢を実現するためには、幾つもの課題を解決する過程が必要である。ぜひ、夢を語り合い、ともに課題を解決する教職員集団でありたい。
イ 一歩前へ
① 教師としての技量を「一歩前へ」
「OECD国際教員指導環境調査2018」によると、日本の小中学校教員は概して「児童生徒に勉強ができると自信を持たせる」「勉強にあまり関心を示さない児童生徒に動機づけをすることができる」「児童生徒が学習の価値を見出せるよう手助けできる」など高い自己効力感をもつ割合が他国に比べ低い傾向にあると述べている。
一年間、向笠小に集う教職員がお互いに切磋琢磨する中で、「授業力が上がった」「子どもたちのやりたいを引き出すことができた」など、教師としての自信をもてるようにしたい。
② 子どもの姿で「一歩前へ」
教育の成果は子どもの姿で語られるべきである。子ども自ら「やりたい」を見つけ、それを子どもたち自身で多様な同学年・異学年交流の機会の中で試行錯誤しながらやり遂げる姿を多く見られるようにしたい。そのような姿が多く見られた時、学校として「一歩前へ」進んだと言えよう。
2020年度向笠小グランドデザイン(案).pdf
子どもたちへのお話
本題に入る前に、先日の「かがやきフェスタ(学習発表会)」についての感想を述べてみたいと思います。一言でいうと、本当に感動しました。最初から最後まで先生たちが前に出ることなく、計画委員を中心に、子どもたちだけで進めることができました。さらに、各学年の発表が、これまで学習したことをふまえ、工夫された内容になっていました。何よりみんなの表情が実に豊かで、発表の声も大きかったです。私は皆さんの成長を感じました。
さて、ここから本題に入ります。始業式の日に、2学期に目指してほしい姿として、この先、どんなに難しいことがあっても逃げずに乗り越えてほしいという願いから「たくましさ」を挙げました。覚えているでしょうか。今日は、このことについてもう少しお話ししてみたいと思います。
「たくましさ」を身につけてほしいとお話ししましたが、正直、自分で「これ、やりたい」と思っても、そのことを最後までやり遂げるというのはなかなか大変です。甘い誘惑が次から次へとおそってきます。例えば、「テストで100点取りたい」と思って勉強を始めても、「面白いテレビ、見たいなあ」とか「ちょっとだけ、ゲームしようかな」「今日1日だけならいいかな」などという思いがふっと思い浮かびます。こういう思いに負けちゃったら「テストで100点」は遠い夢になっちゃいます。だから、そんな甘い誘惑を断ち切るよう、我慢することも大事になってきます。
まずは、自分一人で頑張れるよう、強くなることです。
でも、なかなかそういうわけにもいきません。ではどうするか。友達の力をあてにできるといいですね。
友達に自分のやり遂げたいことを打ち明けて応援してもらうこともそうでしょうし、くじけそうになった時に叱ってもらったり励ましてもらったりすることも友達の力を借りることになるでしょうね。
では、友達の力を借りるためにまず何をすべきか。自分が友達のことを大切にするということです。大切にするということは、友達に興味を持つこと、友達の気持ちを分かってあげようとすることです。これは、そんなに難しいことじゃありません。友達に会ったら挨拶する、顔が曇っていたら「どうしたの?」って声をかける、友達が何か良くないことをしていたら注意してあげる、これだけです。
実は、私も皆さんから力をもらっているのですよ。「校長先生」って声を掛けてくれたり、ニコッとして手を振ってくれたりする子もいます。朝、校門で落ち葉を掃いていると「ありがとうございます」「おつかれさまです」って一声かけてくれる子もいます。「たったこれだけ」のことって思うかもしれませんが、私にとってはこのたった一言がものすごい力になっているし、逆にみんなのためにもっと何かをしたいという気持ちもわいてきます。
いろいろなことをやり遂げる「たくましさ」を身につけるためには、自分自身が強い気持ちを持つことに加え、友達と一緒に頑張ろうとすることも必要で、そのためにはまず自分が友達のことを大切に思うことだよというお話をしました。これで、私のお話は終わりにします。

教師向けの話
本校の子どもたちは、概して学習や運動に前向きで、自分を伸ばそう、成長したいという気持ちを持っています。私たちは、そういった子どもたちの気持ちに寄り添い、「やりたい」が実現できる環境を整えることが何より必要だと考えています。最低限、落ち着いた雰囲気の中で教育活動を実施できるようにはしたいと考えています。
そこで、この日(11月13日)の職員会議で私は、職員に、学校が「荒れる」とか「落ち着いている」などと表現されるが、落ち着いた雰囲気を維持するためには教師は何から取り組めばよいのだろうと話をしました。
以下は、その話の概要です。
1 学校が「荒れる」とは
これまで一般的にどのような状態を「荒れる」と表現してきたのだろうか。私のこれまでの経験では、下記の順に「荒れ」は広がっていくように思う。
(1) 場が荒れる
ゴミが各所に落ちている、靴やトイレのスリッパがバラバラ、
教室の中が雑然としている(机の並び、床の上に文房具などが多く落ちている、掲示物が剥がれたままに)
(2) ことばが荒れる
「てめえ、このやろう」など文字通り言葉が汚い、場をわきまえた話し方ではない(声の大きさ、敬語の使い方・・)、やたらとひそひそ話をする、人を傷つける言葉や侮辱する言葉が飛び交う
(3) 行動が荒れる
小集団で固まり学級全体に帰属しない、授業等を妨害する、他の児童や教師に対する暴言・暴力、器物破損
2 学校が「落ち着いている」とは
「荒れる」ことの反対が「落ち着いている」状態となる。では、どのようなことに心掛ければ「落ち着いた」状態を継続できるのだろうか。
(1) 場を整える
○ 教師が率先垂範して、ゴミを拾う、靴やトイレのスリッパの整頓を行う、教室内の環境整備(学級掲示なども含む)に努める。
○ 「場が整うと気持ちが落ち着く」という感覚を子どもが味わえるようにする。
(2) 美しい日本語を使う
○ 教師自身が「てめえ、このやろう」など汚い言葉や傷つける言葉を使うのは問題外。
○ 教師の声が大きくなるほど、子どもの声は小さくなり、ひそひそ話をするようになる。大声での叱責はもとより、教師による一斉指導は、笑顔で、冷静に、短時間※で…。
※ 以前にも紹介しましたが、オランダイエナプラン教育の創始者であるペーターセンはイエナプラン校を「沈黙と静寂の学校」と評した。子ども同士、子どもと大人が対話することを重視する一方、言葉の氾濫が学習活動の目的を不明瞭にすることを避けねばならないと話している。
○ 子どもたちの言葉遣いに敏感になる。
(3) 子どものエネルギーを正しい方向に向ける
○ 授業は最初の10分間が勝負。子ども自身が、「何のために」「どのように」学ぶのかをしっかり理解できれば、進んで学びに向かう。
○ 意味のある対話(学び合いを意味づける、位置づける、成り立たせる)を意図的に単元の中に組み込んでいく。
保護者向けの話
本校では、磐田市学校運営協議会規則に基づき、9名の協議会委員による協議会を設置しています。本規則では、学校は協議会に対して教育課程や学校経営計画に関する基本方針等を提示し、承認を受けることとなっています。
本日(10月29日)の協議会においては、授業参観後、学校から中間評価結果の説明に加え、来年度以降の教育課程等を検討するうえで大切にしたい2つの方向性について説明をさせていただきました。

概要は、以下の通りです。
(1)子どもも教師も1つのことにじっくりと取り組める環境づくり
○学習指導要領改訂により「学習者主体」が明確になってきた。さらに外国語活動及び外国語科で35時間の増となる。
○地区小学校水泳競技大会や音楽科研究発表会、陸上競技大会においても、じっくりと学習に取り組める環境を整える等の理由から今年度で終わりとなった。
○本校においても、子ども自身が学校行事を企画し、準備・運営できるよう、数と内容を検討する必要があると考える。さらに、時間に追われることのない日課表の工夫も検討していきたい。
(2)小規模校であることを強みにした学校運営
○多様な異学年交流の機会を生み出していきたい。学級以外の新たな人間関係を通して、学級の中では見せなかった違う「顔」を見せる子どもたちも増えるのではないかと考えている。
○学校行事や児童会行事をはじめ様々な教育活動を、異学年交流の機会ととらえて、内容の見直しを図っていきたい。
協議会委員の皆様からは、以下の意見や感想などが出されました。今回出していただいた意見を参考に、これから校内で時間をかけて検討していきます。第3回協議会では、一定の形を提示できるようにしていきます。
○全体的には、子どもたちはよく挨拶ができるのではないかと感じている。一部に自分から挨拶をしない子どもがいるのが気になる。地域全体で続けていく必要がある。
○ホームページ等で学校の様子がよく分かりありがたい。まわりの保護者からも「学校に対して気軽に相談できる雰囲気ができてきた」という声を聴く。
○校長から話が合った2つの方向性を聴き、子どもの可能性がさらに広がる予感がしてワクワクしてくる。地域も協力していきたい。
○水泳大会や陸上大会等の終了に伴い、体力面の低下が懸念される。
○学習者主体という言葉が出てきたが、子どもに何でもお任せではいけない。人と人とのつながり、かかわりなど教師の適切な支援がないと効果的な学びにはならない。